![]()
![]()
|
このオッサンのお陰に間違った方向(日々のせーかつが)へ進んでいったような気がしないでもない。
「アフター・ザ・ゴールドラッシュ」が出たのが1970年ということは、当時11歳。尋常小学校6年生のWeb
とーちゃん。
恐らく72年の「ハーヴェスト」を先に聞いたとして13歳で、旧制中学2年でしょうか。この辺りから75年の「ズマ」までは、ソロから、CSN&Y、バファローまで遡って熱心に聞いたものでした。ちなみに、76年の初来日は武道館へ行きました。未発表だった「ライク・ア・ハリケーン」の演奏中に扇風機が廻っていたのを覚えています。あと、デカイのにビックリしたかな。
|
なんか疲れてきましたー。どして、農家のHPでこんな特集するんでしょー。よく分かりませ〜ん。
が、次。
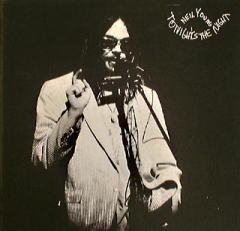 Tonight's The Night 1975 邦題「今宵その夜」73年の録音。 全員が酔っ払って演奏して一切オーヴァーダブ無しで録音されたという。確かに粗い。それで、会社側がボツにしてOn the beach が出たということでした、確か。 結構、売れましたこれも。作品的に良い曲もありますし、ジャケットもいいし、クレージー・ホースのオーバードースで死んだダニー・ウエットンに捧げたというエピソードもリアルな雰囲気を出していました。そのダニー・ウエットンがボーカルを取っているレッツ・ゴー・ダウンタウンって曲も入っています。 ワールド・オン・ア・ストリングが良かったような覚えがあります。 下の画像は中についていたライナー・ノーツの裏写真ですが、長靴を下げたピアノに座るヤングとクレージー・ホースの面々。 といっても、スチールはベン・キース、ギターがあのニルス・ロフグレン。一時期、ロフグレンもはまったような記憶もあります。フィンガーで弾くギタリストで結構ガッツがあって上手かったす。好きなミュージシャン同士が何処かで繋がるというのもいつも驚くことのひとつでした。作品というよりも、フィーリングを個性を好むというRockならではのことかもしれません。 写真の下のほうに名前が入っているのですが、ベン、ラルフ・モリーナ、ビリー・タルボットとロフグレンが重なっていて、その右隣の誰もいないところに、この画像では文字も切れていますが、ダニー・ウエットンと書いてあります。この辺が、いつも包装紙にまで気を使うヤングならではのところですか。  |
このアルバムの後、Zuma、Stills-Young Band のLong May You Run、ライク・ア・ハリケーンのAmerican Stars'n Bars と続く訳ですが、ついて行けたのはその頃まででした。時代もクロス・オーバー、フュージョンの時代になって、ニール・ヤングのでる幕はまったくありませんでしたね。(^o^)
買って全部聞かないうちに捨てたHawks & Doves なんてアルバムもありました。この時期はRock勢は悲惨でした
ストーンズぐらいでしたかグレードを保ったのは。リトル・フィートもその前だったし。マディ・ウォーターズを師としていた者が、ウェス・モンゴメリーだと言い出し、オールマンを弾いていたギター小僧達がみんなジョージ・ベンソンを習い始めた時代です。小指が使えねーとか言いつつ。二十数年前の出来事です。
えーと、ニール・ヤングはこれ以前の「ハーヴェスト」までが、やはり一番良いと思います。そちらのご紹介はまた今度・・・。
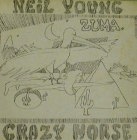 |
Zuma 1975 これは良い出来でした。Don't Cry no Tears Danger Bird、Cortez The Killer 等、聞き物がありました。、 |
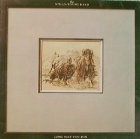 |
Long May You Run 1976 これも駄作とは云われますが、ヤングについては良いと思います。曲もいいし、スティルスと一緒だから丁寧にやっているし。 タイトル曲もいい感じです。「ミッドナイト・オン・ザ・ベイ」は良く聞きました。 |
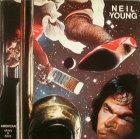 |
American Stars'n Bars 1977 Like A Hurricane しか記憶にありません。確か評論家がヤングのギターを「ヘタウマを突き抜けた情念のいたこ弾き」とか言っていましたがそうかもしれません(笑) 西荻窪のロフトでこれが新譜で出て始めて聞いたのですが、武道館以来始めて聞いた、正規録音版で既に Neil Young からは遠ざかっていたのですが、さすがに大音量でLike〜を聞いた時はコレダ!コレと言って隣の奴の首を絞めた記憶がございます。もちろん酔っていまいた。明け方4時頃。 |